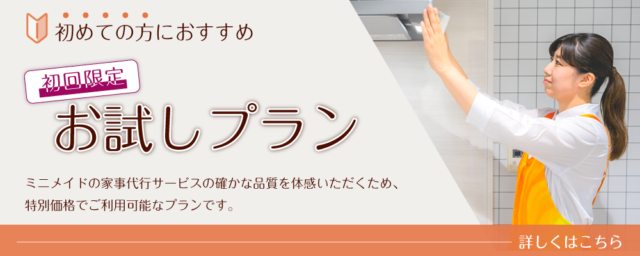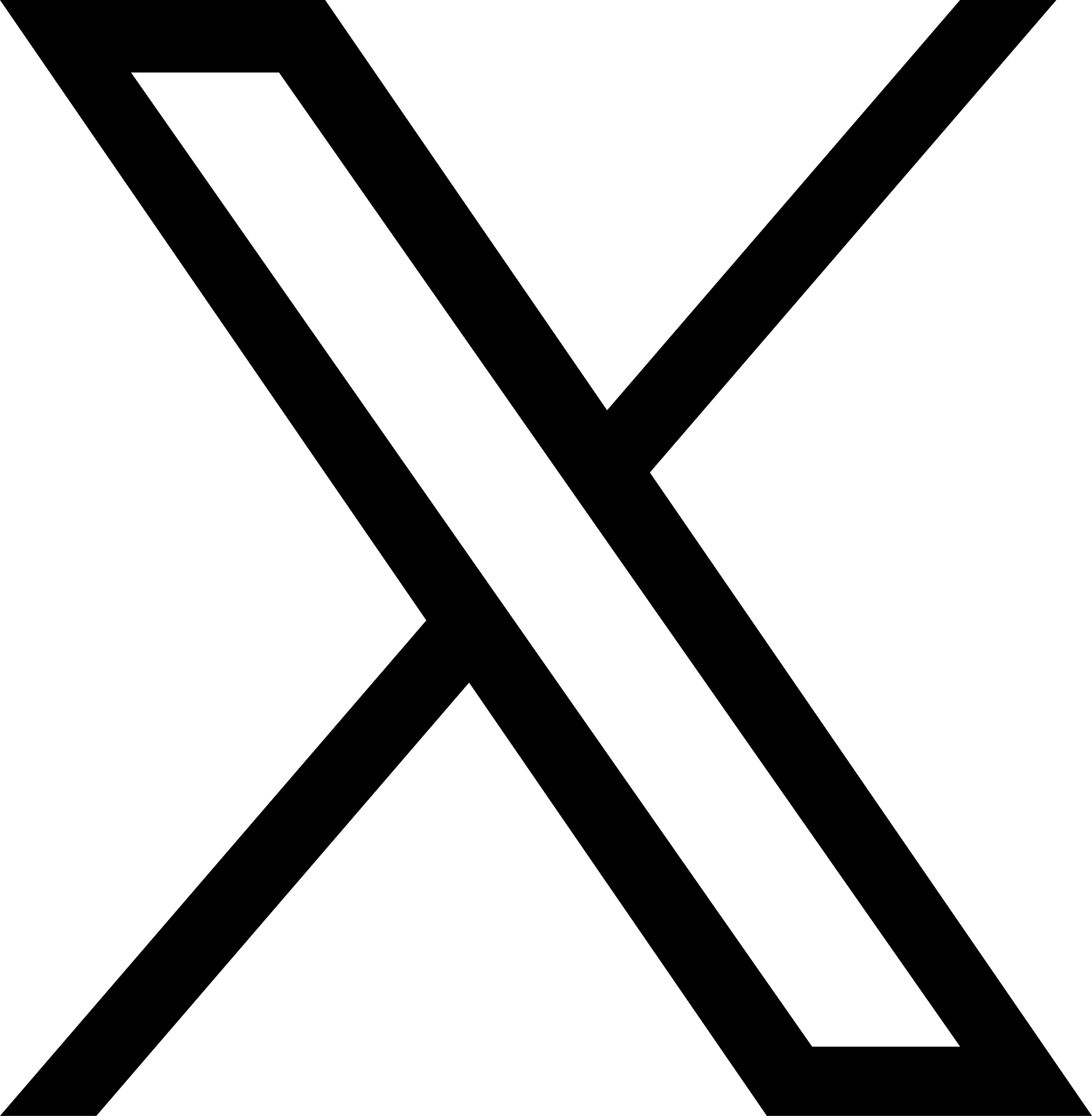もうすぐ梅雨明け!お弁当の食中毒を予防するには!?
ミニメイド直伝!プロの家事術
#お料理の時短&ポイント
梅雨が明け、暑い夏がやってくると、気になるのはお弁当の食中毒です。ジメジメした湿気や高い気温は、細菌性の食中毒を引き起こす原因になることも。特に、お弁当のように作ってしばらく経ってから食べる場合は、注意が必要です。
この記事では、家庭でできる簡単な予防方法やアイデアをご紹介します。毎日のお弁当を、安心・安全に楽しむためのヒントにしてくださいね。

食中毒の原因とリスク
夏の食中毒は、食品に付着した細菌やウイルスが主な原因です。特に、カンピロバクター、ノロウイルス、腸管出血性大腸菌などは、身近な食材から感染することもあります。
湿度も気温も高いこの時期には、調理器具や手指に残った食中毒菌が増殖しやすくなります。特に、お弁当は持ち運び中の温度管理が難しく、食中毒のリスクが高まります。
例えば、こんな点に注意しましょう:
●作ったお弁当を常温で長時間放置してしまう
●調理時、生肉や魚介類を十分に加熱しない
●まな板や包丁を使い回して消毒せずに使ってしまう
食中毒予防の基本ポイント

1、手洗い
調理前に必ず石鹸で手を洗い、清潔な手で調理を行います。途中でもこまめに洗いましょう。手についた目に見えない毒素や細菌は、こまめな手洗いと消毒でしっかり対策を。
2、食材選び
お弁当には、できるだけ新鮮な食材を使うと安心です。特に魚介類や生肉は傷みやすいので注意しましょう。
購入後はすぐに冷蔵庫に入れ、長時間常温に置かないようにします。
3、しっかり加熱調理
お弁当に入れる食品は、中心部まで75℃以上でしっかり火を通すことが大切です。例えば、ウェルシュ菌や黄色ブドウ球菌といった細菌は高温で死滅するため、加熱は食中毒予防の基本です。
お弁当の詰め方と保存方法
1、しっかり冷ます
作った料理は、完全に冷ましてからお弁当箱に詰めましょう。
温かいまま詰めると、温度が下がるまでに時間がかかるうえ、お弁当箱の中が蒸れて細菌が繁殖するリスクが高まります。
2、詰め方に工夫を
仕切りやカップを使い、食品同士が直接触れないようにしましょう。
特に、水分が出やすい生野菜や果物は別の容器に入れることと安心です。
3、保冷グッズの活用
保冷剤や保冷バッグを使って、お弁当の温度を一定に保ちましょう。
保冷バッグの中にアルミホイルを1枚入れておくと、保冷効果がさらにアップしますよ。

特に注意したい食品
1、生もの
生野菜や果物は水分が多く、細菌性食中毒の原因になりやすい食材です。できるだけ避けるか、別の容器に入れて持ち運びましょう。
2、乳製品
チーズやヨーグルトなどの乳製品は、夏場には劣化が早くなります。お弁当には控えると安心です。
3、マヨネーズ系のおかず
マヨネーズを使ったポテトサラダや和え物は、特に注意が必要です。調理器具の殺菌処理が不十分だと、吐き気や嘔吐、腹痛などの症状が出ることも。十分に冷やして保冷対策をしましょう。
食中毒を防ぐためのアイデアレシピ
1、お酢を使った一品
お酢には細菌の繁殖を抑える効果があります。ピクルスや酢の物は、さっぱりとして夏のお弁当にぴったりです。
2、塩分のある食材を利用乳製品
塩分も細菌の繁殖を抑える働きがあります。塩昆布や梅干しをお弁当に入れることは昔ながらの知恵。味のアクセントにもなり大活躍です。
3、常備菜の活用
夏場でも安心して食べられる常備菜を作り置きしておくと便利です。しっかりと火を通したきんぴらごぼうや煮物など、日持ちするおかずを活用しましょう。

暑い季節にさらに気をつけたいポイント
●保冷剤の使用
保冷剤をお弁当に入れることで、食品の温度を低く保ち、細菌の繁殖を防ぐことができます。
●抗菌シートの使用
仕上げにお弁当の上に抗菌シートを乗せるだけで、表面に付着する細菌の抑制につながります。市販の抗菌シートにはかわいらしいデザインのものも豊富です。ぜひ取り入れてみましょう。
●早めに食べる
時間がたつほど、菌は増えやすくなります。お弁当は作ってからできるだけ早めに食べることがポイント。万が一、下痢や吐き気、嘔吐などの症状が出た場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。
お弁当による食中毒を防ぐために
梅雨が明けると、暑い夏の季節がやってきます。気温や湿度が一気に上がり、自然毒や寄生虫といった思わぬリスクも増えてきます。
まな板や調理器具の消毒、しっかりとした加熱、こまめな手洗いと基本的な点を意識することで、日々の対策は可能です。
今回紹介したポイントを参考にして、暑い季節でも家族が安心して食べられるお弁当を作りましょう。
関連記事
-

ミニメイド直伝!プロの家事術
#道具を使った時短お掃除
#お掃除の時短&ポイント
-

ミニメイド直伝!プロの家事術
#お料理の時短&ポイント
-

ミニメイド直伝!プロの家事術
#お掃除の時短&ポイント