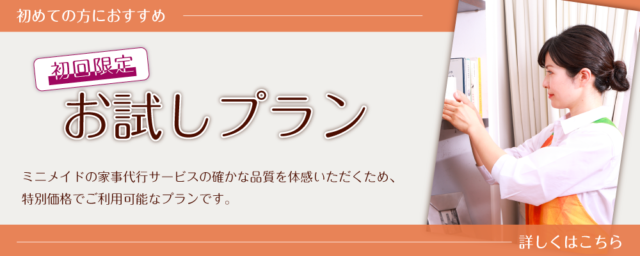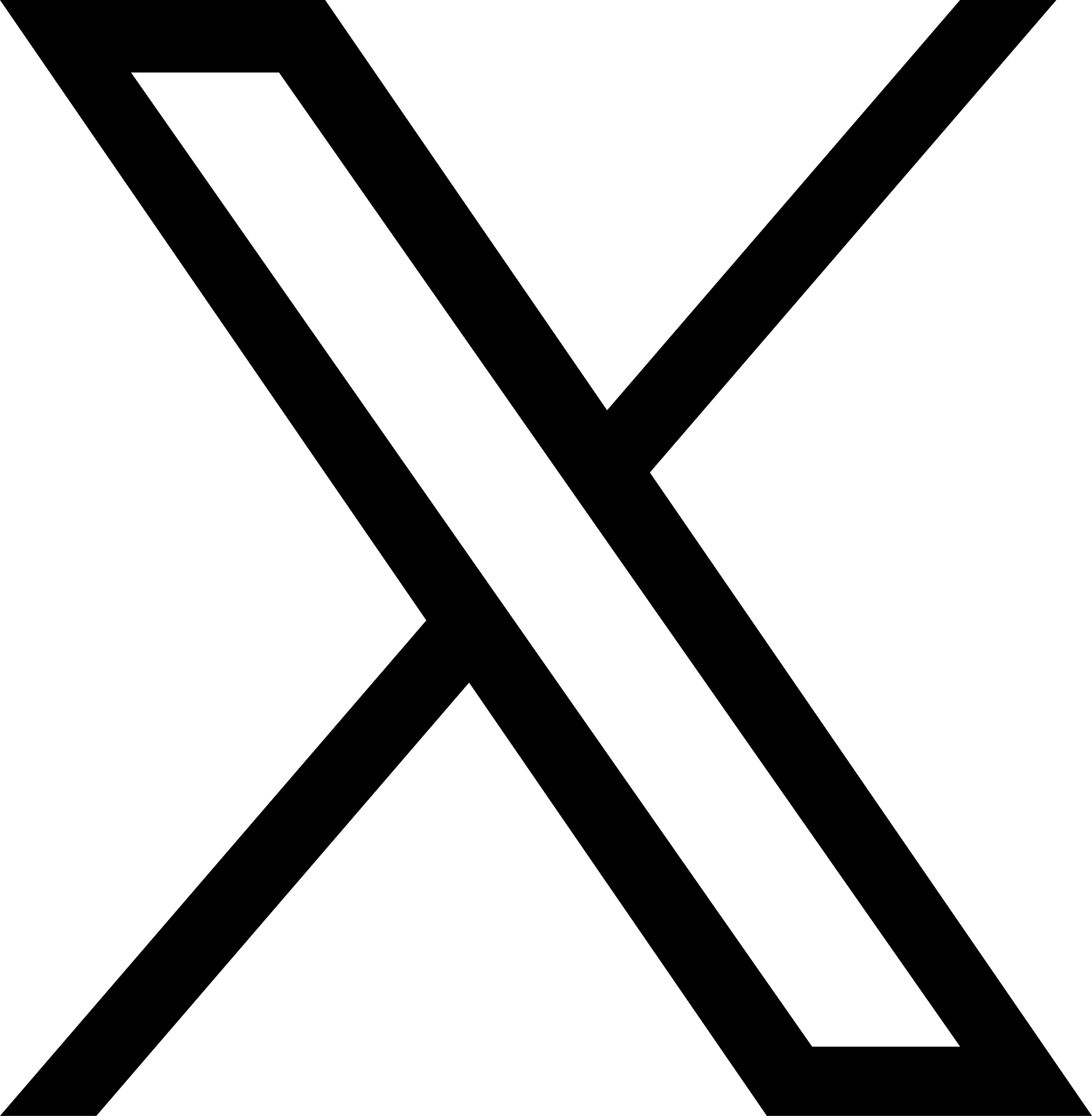整理整頓のコツと手順を徹底解説!
ミニメイド直伝!プロの家事術
#お掃除の時短&ポイント
整理整頓・整理収納は生活の質を向上させる重要な要素です。
しかし、多忙な日常の中で整理整頓された状態を維持することは難しいと感じている方も多いのではないでしょうか?
本記事では、整理整頓・整理収納のコツを詳しくご紹介します。

目次

「整理整頓が苦手」
「仕事から疲れて帰ってきても部屋が散らかっているせいで、ストレスを感じる」
そんなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
整理整頓を始めたものの途中で挫折してしまったり、きれいな状態を保てない方もいるかもしれません。
今回の記事では、整理整頓に苦手意識がある方でもスムーズに取り組めるよう、以下の2つのポイントに絞って徹底解説します。
・整理整頓をスムーズに進める7つのコツ
・整理整頓の3つの基本ステップ
家事代行サービスを提供しているミニメイドならではのノウハウとプロの視点から整理整頓のコツをお伝えします。
整理整頓に苦手意識がある方もこの手順とコツを参考にすることで、スムーズに整理整頓ができるようになるはずです。
1. 整理整頓をはじめる前に知っておきたいよくある失敗例
収納グッズを最初に買ってしまう

「整理整頓するぞ!」と意気込んで、整理整頓を始める前に収納グッズを買ってしまう人は少なくありません。
ですが、いざ使おうとするとサイズが合わなかったり、想定していた収納に合わなかったりして、結局使わないケースも多いのです。
その結果、収納グッズ自体が置き場を取ってしまい、むしろ部屋を散らかす原因になってしまうことも。
こうした失敗を避けるためには、まず部屋の整理整頓をして物の量を把握し、本当に必要な分だけ収納グッズを購入するのがポイントです。
捨てられなくて作業が進まない
「まだ使えるから」「もったいないから」と思って物を捨てられず、いつまでも整理整頓が進まないケースもよくあります。
こうした場合は、自分なりにルールを決めるのがおすすめです。
たとえば「複数あるものは1つ残して他は手放す」など、明確な基準を作ると判断がしやすくなります。
どうしても捨てることに抵抗がある場合は、人に譲ったり、フリマアプリで売ったりと「誰かに活用してもらう」方法を取るのも一つの手です。
罪悪感が減り、前向きに整理整頓を進められます。
2.整理整頓の3つのステップ
では、実際に整理整頓を始める際の基本的な3つのステップをご紹介します。
この手順通りに進めることで途中で挫折することなく、効率的に整理整頓を進められるでしょう。
①全部出し:まずは『持っているもの』の全体量を把握する
整理整頓の最初のステップは、しまってある物を一度すべて外に出すことです。
クローゼットの引き出し一つ、キッチン収納など整理整頓する場所を決めて、そこにしまってある物をすべて外に出しましょう。
この作業の目的は、自分が何を持っているのか、どのくらいの量があるのかを正確に把握することです。
すべてを外に出すことで、使う頻度が少ない物や存在を忘れていた物も可視化できます。
「どこから手をつけたらいいか分からない」「一度始めたら終わりが見えなくなりそう」と不安な方は、まずは引き出し1つや小さめの棚1つなど、狭いスペースから始めるのがおすすめです。
小さな収納から徐々に大きい収納に取り掛かるようにすることでモチベーションに繋がります。

②分類:『使う・使わない・考え中』で仕分けする

すべての物を出したら、今度は以下の3つのグループに分類していきます。
・使う: 日常的に使っている物、これからも使う予定がある物
・使わない: 1年以上使っていない物、今後も使う予定がない物、壊れている物
・考え中: 使うか使わないかすぐに判断できない物、思い出の品など
この作業で重要なのは、「最後に使ったのはいつか?」「今後も使う予定がありそうか?」を基準に判断することです。
「いつか使うかも」「もらい物で捨てにくい」など、判断がつかない物もあると思います。
そういった物は一旦、「考え中」のグループに分類し、あとで改めて判断する時間を取るようにします。
こうすることで、作業のスピードを保ち、途中で整理整頓の作業が止まるのを防ぐことができます。
③収納:モノの定位置を決めてしまう
②のステップで「使う」に分類した物を収納していきます。
ここで重要なのは、ただしまうだけでなく以下のポイントを意識して収納することです。
・毎日使う物:取り出しやすく、元に戻しやすい場所にしまう
・年に数回しか使わない物:収納の奥や上段など、使用頻度の低い場所にしまう
〇種類で分ける
例えば、食器は食器棚、洋服はクローゼット、文房具は引き出しなど、種類ごとにグループ分けして収納します。
特に、書類は「取扱説明書」「学校関連」「公共料金」など具体的なカテゴリーに分けてファイルボックスにしまうと、あとで探す手間が省けます。
3. 整理整頓のコツ7選
①キッチンや洗面台下の収納から整理する
キッチンや洗面台の下は収納すべきもののカテゴリーが限られていて、スペースも比較的小さいので取り掛かりやすいです。
また、処分の判断が難しい、「思い出のもの」が収納されているわけではないので作業が進みやすいというメリットも。
どこから整理整頓を進めたら良いか分からない方は、まずはキッチンや洗面台下から整理整頓するのがおすすめです。

②物の定位置を決める
すべての物に定位置を設けることが、きれいな部屋を維持するための最も重要なポイントです。
「このボールペンはここ」「この書類はあのファイルボックス」というように、使ったら必ず戻す場所を具体的に決めておきましょう。
定位置が決まっていると片付けに迷いがなくなり、物を元の場所に戻せるようになります。
家族がいる場合は全員で定位置を共有することで、協力してきれいな状態を維持しやすくなります。
③中身が見えるケースを使う
収納ケースを選ぶ際は、中身が見える透明なタイプを選ぶのがおすすめです。
中身が見えないケースに物をしまうと、結局どこに何があるか分からなくなり、探す手間が発生したり、同じ物を買ってしまったりすることがあります。
特に、ストックしている食品や洗剤、常備薬などは、中身が見えないと何が入っているか忘れ、気づいたら使用期限が切れていた、という事態にもなりかねません。
もし中身が見えないケースを使う場合は、中身がわかるように「ラベリング」しておくのがおすすめです。
ラベリングは物を探す時間を短縮できるうえに、元の場所に戻す習慣づけにも繋がります。

④毎日使うものは出し入れしやすいようにしまう
日常的に使う頻度が高い物は、取り出しやすく、そして使ったあとにすぐに元の場所に戻しやすいように収納することが大切です。
例えば、よく使う筆記用具はペン立てに立てておく、毎日使うカバンはフックにかけておくなど、ワンアクションで出し入れできる工夫をしましょう。
これにより散らかりの原因となる「出しっぱなし」を防ぎ、きれいな状態を自然と保てるようになります。
⑤1年以上使っていないものは処分する
1年以上使っていない物は、今後も使わない可能性が高いです。
物を手放す際の明確な判断基準として、「1年以上使っていないものは処分する」というルールを設定しましょう。
「いつか使うかも…」という考えは、物を溜め込む原因になります。
このシンプルな基準を設けることで、処分するか否かの判断がしやすくなり、作業がスムーズに進みます。

⑥思い出のものや書類の整理整頓は後回しにする
アルバムなどの思い出の品や契約書などの書類は、一つ一つに目を通し始めると時間がかかったり捨てるかどうかの判断に迷ったりしやすいです。
こうした時間がかかりそうなものは、一旦「保留用の箱」などに入れておき、整理整頓の作業後半や、別の日にまとめて取り組むようにしましょう。
まずはキッチン周りや洗面所など簡単に判断できる場所から着手することで、スムーズに作業を進められます。
⑦物を増やさないためのルールを設ける
新しい物がどんどん増えてしまうと、どんなに整理整頓を頑張っても、いずれ収納スペースが足りなくなり、再び散らかり始めます。
物を増やしすぎないためのマイルールを決めておくことが、きれいな部屋を維持する秘訣です。
例えば、以下のようなルールが有効です。
・ワンインワンアウトの法則:新しい物を1つ買ったら、古い物を1つ捨てる
・今ある物で代用できないか検討する:新しい物を買う前に、「本当に必要か?」「今持っている物で代用できないか?」と考える習慣をつける
自分に合った無理のないルールを見つけて実践してみましょう。

4.エリア別の片付けのコツ
キッチン
カトラリーなどの細かいものは収納ボックスでカテゴリー別に分けて収納すると取り出しやすく、きれいな状態を保ちやすいです。
フライパンや鍋などの調理器具はファイルボックスを使って立てて収納すると良いでしょう。
使用頻度が低い食器は戸棚の奥や高い位置に収納し、よく使う食器は手前に収納することで取り出しやすくなります。

リビング

リビングはものが多く、散らかりがちです。
リビングもカテゴリーごとに分けて収納しておくと、どこに何があるかが分かりやすくなります。
例えば、書類や文房具、リモコン類などに分けてそれぞれ専用のボックスに収納しておきます。
カゴなどを1つ用意し、何でも入れて良い「フリースペース」を作っておくと物が散らかるのを防げて家族も片付けしやすくなります。
クローゼット
使用頻度やシーズンに合わせて収納の仕方を変えます。
例えば、今季の洋服や使う頻度が多い下着、重たいものは中段や下段に収納し、取り出しやすくします。
反対に使用頻度が少ないものやシーズンオフの洋服は上段に収納しておきます。
洋服が多く、収納できない場合は連結できるハンガーを使用するのもおすすめです。
省スペースになり、収納力が上がります。

今回の記事では、整理整頓が苦手な方でも実践できる3つのステップと、スムーズに進めるためのコツ、きれいな状態を維持するための方法をご紹介しました。
もし、「自分一人ではなかなか整理整頓の時間がとれない」「効率よくきれいにしたいけれど自信がない」と感じる場合は、プロに頼るのも有効な方法の一つです。
ミニメイドサービスでは、家事代行のお試しサービスもご用意しています。
プロのサポートを試したい方は、利用を検討してみてはいかがでしょうか。
関連記事
-

ミニメイド直伝!プロの家事術
#お掃除の時短&ポイント
-

忙しい方必見!時短お掃除術
#お掃除の時短&ポイント
-

忙しい方必見!時短お掃除術
#道具を使った時短お掃除