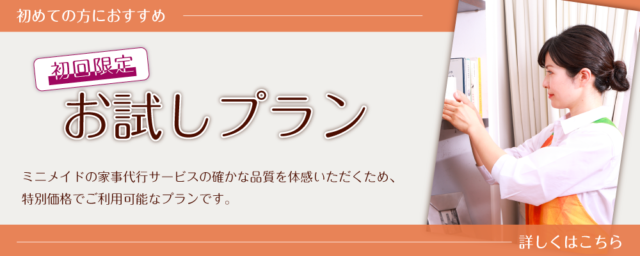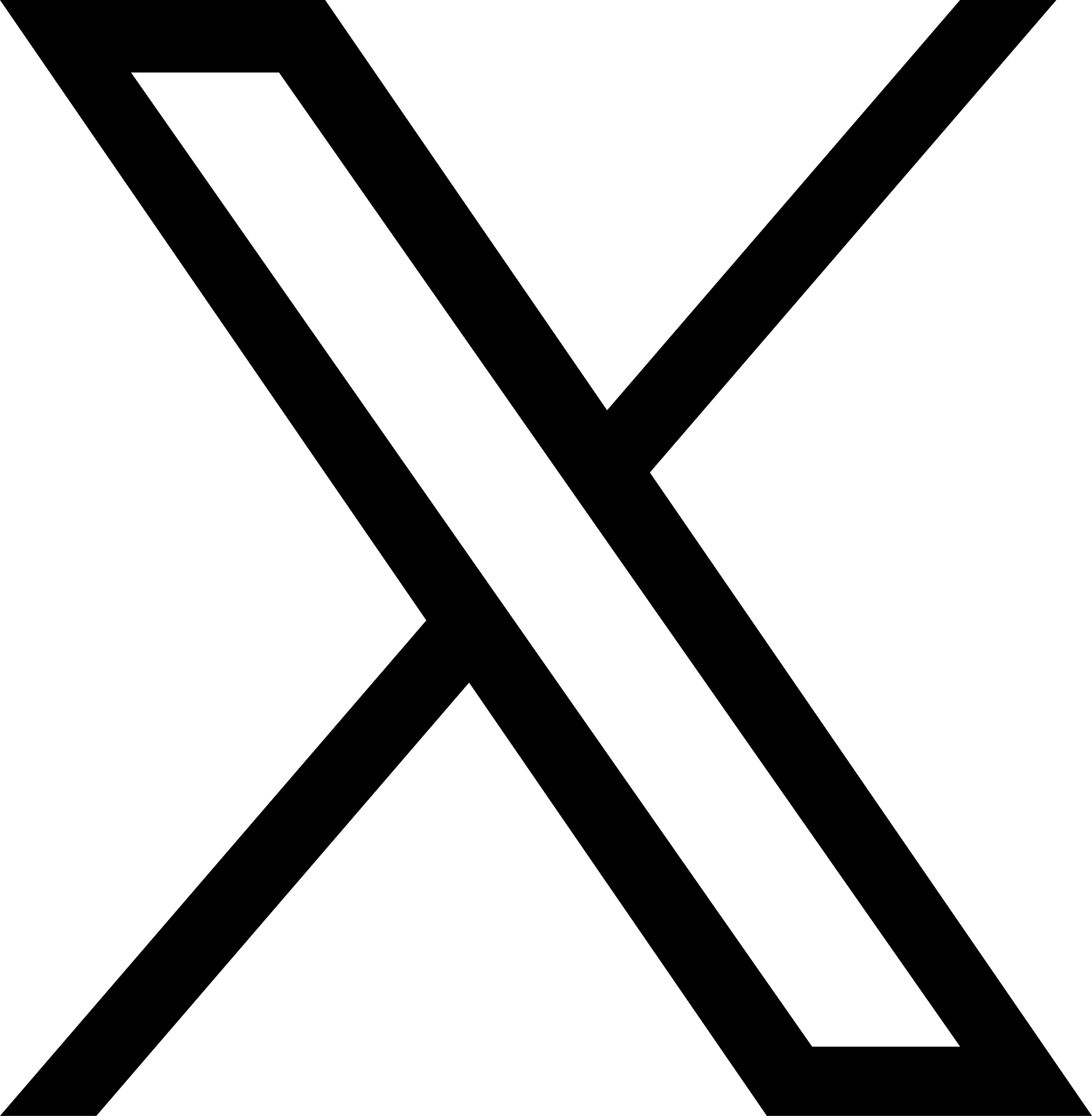今日からできる 整理整頓の手順とコツを徹底解説!
ミニメイド直伝!プロの家事術
#お掃除の時短&ポイント
「整理整頓が苦手」「散らかった部屋でストレスを感じる」といったお悩みはありませんか?
今回の記事では家事代行サービスを提供しているミニメイドならではのノウハウとプロの視点から、以下の3点を徹底解説します。
・整理整頓の3つの基本ステップ
・整理整頓をスムーズに進める4つのコツ
・整理整頓後の部屋をきれいに保つ3つの秘訣
この記事を読めば、整理整頓に苦手意識がある方もスムーズに作業できるようになるはずです。

1. 整理整頓のメリット

そもそも、なぜ整理整頓が必要なのでしょうか?
単に部屋がきれいになるだけでなく、日々の生活や心の状態にも良い影響を与えてくれるなど、整理整頓にはメリットがあります。
探し物が減る
前に使ったはずの物が見当たらない…といった経験はありませんか?
整理整頓されていればどこに何があるかが一目でわかり、物を探すストレスから解放されます。
また、探し物をする時間が減る分、家事や仕事などに時間を割けるというメリットもあります。
無駄遣いが減る
整理整頓することで、自分が何をどのくらい持っているかを正確に把握できるようになります。
そのため、「すでにもっているのに同じ物を買ってしまった」という無駄な買い物が減ります。
本当に必要な物だけを購入する習慣が身につき、結果的に節約にも繋がるでしょう。
2. 整理整頓の3つのステップ
では、実際に整理整頓を始める際の基本的な3つのステップをご紹介します。
この手順通りに進めることで途中で挫折することなく、効率的に整理整頓を進められるでしょう。

①全部出し:まずは『持っているもの』の全体量を把握する
整理整頓の最初のステップは、しまってある物を一度すべて外に出すことです。
クローゼットの引き出し一つ、キッチン収納など整理整頓する場所を決めて、そこにしまってある物をすべて外に出しましょう。
この作業の目的は、自分が何を持っているのか、どのくらいの量があるのかを正確に把握することです。
すべてを外に出すことで、使う頻度が少ない物や存在を忘れていた物も可視化できます。
「どこから手をつけたらいいか分からない」「一度始めたら終わりが見えなくなりそう」と不安な方は、まずは引き出し1つや小さめの棚1つなど、狭いスペースから始めるのがおすすめです。
小さな収納から徐々に大きい収納に取り掛かるようにすることでモチベーションに繋がります。
②分類:『使う・使わない・考え中』で仕分けする
すべての物を出したら、今度は以下の3つのグループに分類していきます。
・使う: 日常的に使っている物、これからも使う予定がある物
・使わない: 1年以上使っていない物、今後も使う予定がない物、壊れている物
・考え中: 使うか使わないかすぐに判断できない物、思い出の品など
この作業で重要なのは、「最後に使ったのはいつか?」「今後も使う予定がありそうか?」を基準に判断することです。
「いつか使うかも」「もらい物で捨てにくい」など、判断がつかない物もあると思います。
そういった物は一旦、「考え中」のグループに分類し、あとで改めて判断する時間を取るようにします。
こうすることで、作業のスピードを保ち、途中で整理整頓の作業が止まるのを防ぐことができます。
③収納:モノの定位置を決めてしまう
②のステップで「使う」に分類した物を収納していきます。
ここで重要なのは、ただしまうだけでなく以下のポイントを意識して収納することです。
・毎日使う物:取り出しやすく、元に戻しやすい場所にしまう
・年に数回しか使わない物:収納の奥や上段など、使用頻度の低い場所にしまう
〇種類で分ける
例えば、食器は食器棚、洋服はクローゼット、文房具は引き出しなど、種類ごとにグループ分けして収納します。
特に、書類は「取扱説明書」「学校関連」「公共料金」など具体的なカテゴリーに分けてファイルボックスにしまうと、あとで探す手間が省けます。
3. 整理整頓をスムーズに進めるためのコツ4選
ここからは、整理整頓の作業を効率的に進めるための具体的なコツを4つご紹介します。

①収納グッズは最後に買う
整理整頓を始める前に収納グッズを用意しておきたい方もいるかもしれませんが、収納グッズを購入するのはあとにしましょう。
事前に購入しておいて、いざ物を入れたらサイズが合わなかったり、うまく使いこなせなかったりするケースも少なくありません。
まずは手持ちの収納ケースを使い、物の量や収納スペースを把握してから本当に必要な収納グッズを買い足すようにすると無駄を減らせます。
②中身が見えるケースを使う
収納ケースを選ぶ際は、中身が見える透明なタイプを選ぶのがおすすめです。
中身が見えないケースに物をしまうと、結局どこに何があるか分からなくなり、探す手間が発生したり、同じ物を買ってしまったりすることがあります。
特に、ストックしている食品や洗剤、常備薬などは、中身が見えないと何が入っているか忘れ、気づいたら使用期限が切れていた、という事態にもなりかねません。
もし中身が見えないケースを使う場合は、中身がわかるように「ラベリング」しておくのがおすすめです。
ラベリングは物を探す時間を短縮できるうえに、元の場所に戻す習慣づけにも繋がります。
③1年以上使っていないものは処分する
1年以上使っていない物は、今後も使わない可能性が高いです。
「いつか使うかも…」という考えは、物を溜め込む大きな原因になります。
物を手放す際の明確な判断基準として、「1年以上使っていないものは処分する」というルールを設定しましょう。
このシンプルな基準を設けることで、処分するか否かの判断がしやすくなり、作業がスムーズに進みます。
④思い出のものや書類の整理整頓は後回しにする
アルバムなどの思い出の品や契約書などの書類は、一つ一つに目を通し始めると時間がかかったり捨てるかどうかの判断に迷ったりしやすい傾向があります。
こうした時間がかかりそうなものは、一旦「保留用の箱」などに入れておき、整理整頓の作業後半や、別の日にまとめて取り組むようにしましょう。
まずはキッチン周りや洗面所など簡単に判断できる場所から着手することで、スムーズに作業を進められます。
4. 整理整頓後の部屋をきれいに保つコツ3選

せっかく整理整頓した部屋も、すぐに散らかってしまっては意味がありません。
きれいな状態を維持するために、日常生活で意識したい3つのコツをご紹介します。
①毎日使うものは出し入れしやすいようにしまう
日常的に使う頻度が高い物は、取り出しやすく、そして使ったあとにすぐに元の場所に戻しやすいように収納することが大切です。
例えば、よく使う筆記用具はペン立てに立てておく、毎日使うカバンはフックにかけておくなど、ワンアクションで出し入れできる工夫をしましょう。
これにより散らかりの原因となる「出しっぱなし」を防ぎ、きれいな状態を自然と保てるようになります。
②物の定位置を決める
すべての物に定位置を設けることが、きれいな部屋を維持するための最も重要なポイントです。
「このボールペンはここ」「この書類はあのファイルボックス」というように、使ったら必ず戻す場所を具体的に決めておきましょう。
定位置が決まっていると片付けに迷いがなくなり、物を元の場所に戻せるようになります。
家族がいる場合は全員で定位置を共有することで、協力してきれいな状態を維持しやすくなります。
③物を増やさないためのルールを設ける
新しい物がどんどん増えてしまうと、どんなに整理整頓を頑張っても、いずれ収納スペースが足りなくなり、再び散らかり始めます。
物を増やしすぎないためのマイルールを決めておくことが、きれいな部屋を維持する秘訣です。
例えば、以下のようなルールが有効です。
・ワンインワンアウトの法則:新しい物を1つ買ったら、古い物を1つ捨てる
・今ある物で代用できないか検討する:新しい物を買う前に、「本当に必要か?」「今持っている物で代用できないか?」と考える習慣をつける
自分に合った無理のないルールを見つけて実践してみましょう。
今回の記事では、整理整頓が苦手な方でも実践できる3つのステップと、スムーズに進めるためのコツ、きれいな状態を維持するための方法をご紹介しました。
もし、「自分一人ではなかなか整理整頓の時間がとれない」「効率よくきれいにしたいけれど自信がない」と感じる場合は、プロに頼るのも有効な方法の一つです。
ミニメイドサービスでは、家事代行のお試しサービスもご用意しています。
プロのサポートを試したい方は、利用を検討してみてはいかがでしょうか。
関連記事
-

ミニメイド直伝!プロの家事術
#お掃除の時短&ポイント
-

忙しい方必見!時短お掃除術
#お掃除の時短&ポイント
-

忙しい方必見!時短お掃除術
#道具を使った時短お掃除